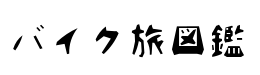あおり運転は受け取り方に依存する傾向あり
交通トラブルの代表格として認知度も非常に高いのが、煽り運転と言われる行為です。
被害者がドライブレコーダーの映像をインターネット上に公開するそういった行為が流行したこともあり、認知度が格段に増えた交通トラブルと言えるでしょう。
しかし、実はこの煽り運転に法律上のはっきりとした定義がないということは、意外と知られていません。
今のところ、車間距離不保持や急ブレーキ禁止違反といった交通違反、もしくは暴行罪や危険運転致死傷罪などで摘発されていますが、あくまでもあおり運転という犯罪は存在しないのが現状です。
煽り運転が原因で被害者が怪我をしたり死に至ったということが報道を賑わせることもあり、今後の改善が見込まれる危険運転とされています。
しかし煽り運転は受け取り側の感覚に依存する部分も多いため、決まりを設けるのが難しい交通ルールと言えるのも事実です。
車間距離を詰めたつもりがなくても、前の車からすれば煽られている状態にとれるかもしれませんし、たまたま速度が低下して車間が縮まったことを煽られたと勘違いされるケースも十分にありえます。
明確な定義がない以上、いちライダーとしては周囲をの苛立ちを買い煽られるような運転を避けることはもちろんのこと、煽られていると勘違いされないような運転を心掛けることがとても大切になります。
最近は車間が詰まるとあおり運転?
煽り運転の最近の傾向として知っておきたいのは、世間が煽り運転に非常に敏感になっているということです。
東名高速道路での煽り運転によって起きた事件がきっかけとなり、メディアが煽り運転という言葉を多く使い世間に定着しました。
車間が通常より少し詰まっているというだけでも受け取り側の印象次第で煽り運転と言われ、ドライブレコーダーの映像をインターネットに流されるという可能性もあります。
バイクですり抜けや無理な追い越しをする、車間距離を詰めるなど、嫌がらせと受け取られる行為をすると、知らない間にナンバープレートも含めネットに晒されてしまう危険があるんです。
バイカーとしてできること
煽り運転対策としては、バイカーは愛車にドライブレコーダーをつけることをおすすめします。
特におすすめなのは、車両前後の両方にカメラがつけられるものです。
車の運転ではあまり意識しませんが、バイクへのあおり運転は前でも後ろでも行われることがあります。
ドライブレコーダーを装着して撮影していることを周囲にアピールすることで、トラブルを未然に防ぐ抑制効果が期待できます。
また、実際にあおり運転の被害にあった場合に、証拠として残すこともできるでしょう。